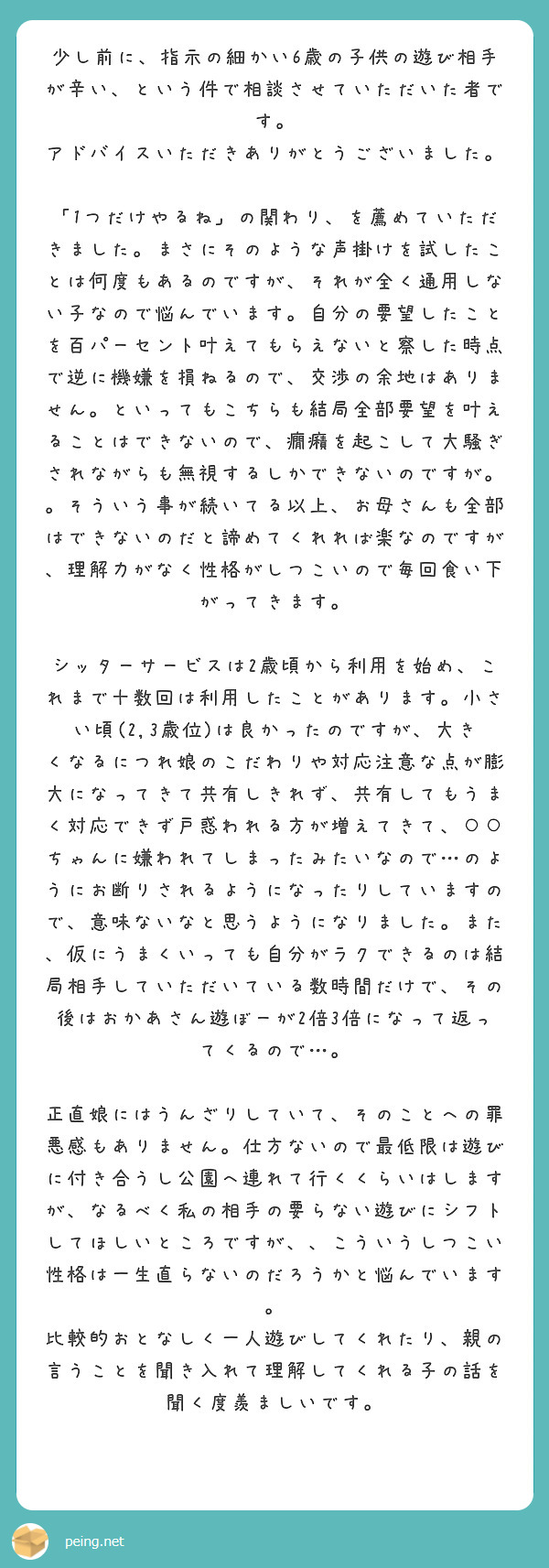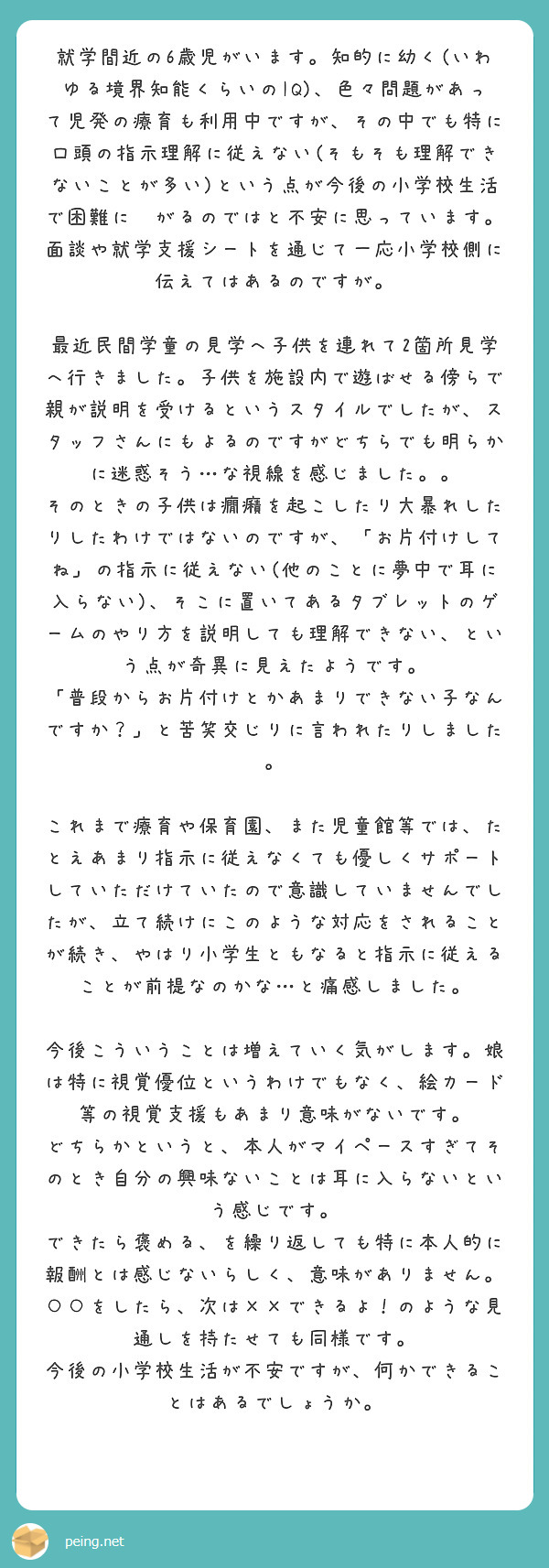回答お待たせしました。 再度の質問をいただき、ありがとうございます。 お母様やお子様のまわりに支援してくださる方が いらっしゃる中、私たちに相談をしていただき 嬉しく思います。 3月も残り少なくなりました。 卒園式が終わり、長い春休みで疲弊されているのではないか と心配しています。 さて、今回のお悩みです。 園では、お友達と仲良く遊ぶことができるのに お母様に対しては要求が強く、疲れてしまうのですね。 前回、提案させていただいたアドバイスもお母様は 実践済み。 どれもうまくいかなくて、本当に困っていらっしゃる。 こどもは、100人いれば100通りの育ちをしています。 私もたくさんのお子さんたちを見てきましたが、 1人として同じ成長の道すじをたどるお子さんはいませんでした。 毎回試行錯誤です。 お子様の場合は、園では比較的自分を抑えてがんばって 集団に適応しようとしているから、あまり問題は指摘されない のかもしれません。 きっと、外で自分を抑えている分、おうちでは自分の思うように 過ごせるというようになっているのではないかと想像します。 以前担当していたお子さんのエピソードです。 成長はゆっくりでしたが、外ではとってもおとなしくて問題はほとんどありませんでした。 でも、そのお母さんの悩みは、 「家にいるとずっとなんで?なんで?の質問攻撃で本当に疲れるんです」とおっしゃっていました。 「なんで?」に答えても、また「どうして?」「なんで?」と続くのだそうです。 お母様と同じように、こどものいうことに一生懸命答えようとして疲弊されてました。 私は、言いなりになる必要はないことをお伝えしました。 数回答えた後、”お母さんは、もう疲れたからお話したくないな” と伝えてみましょうと提案をさせていただきました。 ”お母さんは”を主語にして、お母さんが嫌なこともきちんとこどもに伝えましょうとお話ししました。 繰り返し伝えた結果、”なんで?”と聞くことはあっても何度も何度も聞くことはなくなってきたそうです。 それから半年位したころ。私は、学校での様子を見に行きました。 国語の授業でプリントに取り組んでいました。 3行ほどの文章を読んだ後、3問の質問に答える形でした。 2問目の質問の答えは、”すこしだけたべました”と書けばよいのですが 「う~~~ん」と悩んでいました。 先生が「どこに書いてあるかな?」と促すと「ここ」と文を指さしするのです。でも、書こうとしない。少し待っていたら 「すこしってどのくらいなのか、ぼくはわからない」 って言ったのです。 なんで?どうして?ばかりだった子が じっくり考えてわからないことをことばで伝えることが できました。 先生と私は顔を見合わせて、喜び合いました。 「そうだよね」「すこしってみんな違うよね」と先生が伝えると 「うん!」とわかってもらった満足感からか笑顔を見せてくれました。 その上で、「みんなのすこしはわからないけど、ここの文をこのまま書けばいいよ」と先生から教えてもらって、納得して書き上げることができました。 お母さんにこのことをお伝えし、 なんで?どうして?の嵐だったころを振り返りました。 嵐の中にいるとずっと続く気がして不安でした。 今から考えると、卒園と入学という環境の変化の不安から なんで?どうして?にこだわっていたのかもしれません。 学校になれ、先生になれた今、そんなふうに先生に伝えることが できるようになったことを嬉しく思います。 とおっしゃっていました。(少し内容は変えています) このお子さんのことを知らない人からすると、 それくらいのことで~と思うかもしれません。 そばで成長を見守っていたお母さんや先生、私にとっては 大きな成長で嬉しい出来事でした。 お母様も、まわりにいらっしゃる療育や園で 支援してくださっている方から 「いつもは~だけど、今日は○○でした」 「とってもいい笑顔で△△して楽しんでました」 「お友達と~と言いあいながら、遊んでました」等 お子様の素敵なエピソードを聞くことはないでしょうか。 毎日一緒にそばにいるお母様には見えずらくても 普段関わってくださっている方は、お子様の ほんの少しの成長を発見し、伝えてくださっていると思います。 ほんの少しの成長を喜び合える誰かが お母様にいらっしゃるといいなあと思います。 残念ながら、この相談ではできないことが苦しいです。 お母様は、これまで関わりの工夫は十分にされてきています。 関わりの工夫だけでがんばるのは、心が疲れてしまいます。 お子様は、どちらかというと神経が休まりにくい、 エネルギッシュなタイプと想像しています。 気持ちが盛り上がっている状況から、落ち着く、しずめるには 関わりの工夫よりも環境の工夫の方が効果がある場合もあります。 エステや整体等、ストレスフルな状況を断ち切るために 光や音、香りの環境を整えていたりします。 光~柔らかな温かみのある光、間接的な照明 音~ゆったりとした静かな音楽 香り~アロマ等 実は、発達に凸凹のあるお子さんたちに向けて、 開発されたアロマがあるのです。 tobiracoの療育アロマ https://tobiraco.co.jp/item/aroma_seiyu/ この商品でなくても、少し部屋の照明を落とし お母様もお子様も好きな香りにつつまれる時間をつくって 気持ちを落ち着ける。 お母様に余裕があるなら、ゆっくりお子様の手足を マッサージしてあげる。 もしかしたら、お子様もお母様にやってくれるかも しれません。 4月から新しい環境での生活が始まりますね。 小学校に入ると、幼児期とは違って親の目が 届きづらくなり、学校の中でのことは把握しづらくなります。 その上、発達に凸凹のあるお子さんは、 不安を上手に伝えることができないことが多いです。 表面に出ている行動の裏には、不安があるのかもしれない と考えて、不安な気持ちから安心できるように 学校の先生とお話しする機会を作っていかれると よいかもしれません。 またお話を聞かせてください。 子育ての伴走者でありたいと思い、応援しています。
スポンサーリンク
しあわせお母さんプロジェクトさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
スポンサーリンク