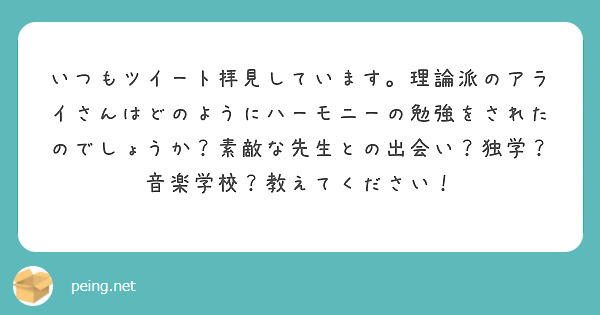これは簡単に答えるのが難しい!すごく長くなります。 まず素直な告白として、アライさんは全く理論派じゃないんですよね。ただ、アライさんが見かけ上は理論派に見えるというのはなんとなく理解できます。でも実際にはふわっとした感覚にほぼ全面的に頼って書いていてりする。 さておき、そしてそうでありながらも、もちろん理論には興味がありました。後付けながらも結果的にある程度は理論を学んだので、自分が書いた曲に起きていることはそれなりにポピュラー音楽理論の共通言語で説明できます。アライさんに限らず理論というものはいつも現象の後付けなのかもしれませんけどね。 理論から曲が生まれることがないとは言いませんが、どちらかというとレアケースだと思います。音楽は基本的に自然言語なので。ただいずれにしても、理論を知っておくとやはり共通言語で説明できたり記譜できたりします。誰かと共同で音楽を作る時に便利ですね。 さてハーモニーの学び方、これも理論と同じく独学といえば独学ですね。ヤマハでピアノを習っていたとかいったような経験はないし、音楽系の学校で正規教育を受けたことはないです。そういう意味では独学です。 幼い頃、家族がピアノを習っていたりバイオリンをやっていたりしていて他にもいろいろな譜面や楽器があったので、そのへんを勝手に読んで、わからないなりに親しんでいたということはありました。ピアノにいつでも触ることができて、コード理論などの入門書が手元にあったのはよかったかもしれません。それらを読んで弾くことで、ナチュラルスケールのダイアトニックコード程度なら、小学生ながらも漠然と理解していたので。 アライさんの最初の楽器は小学生の頃のアコースティックギターで、Fのバレーコードくらいはできるという感じでした。中学でギターをやる友達が増えて、アライさんはベースをやりたくてバンドを組んで高校卒業までやってました。大学ではブラスセクションやパーカッションまでいるような大所帯のバンドでベースを弾いていました。オリジナルのフュージョンバンドとかもやってましたね。楽しかったですし色々具体的に経験を学びました。 理論やハーモニーなどはそんな感じでこれまであったフレンズたちから学んだ、というのが正直な話ホントのところです。これは別に美談にしようとかいうことではなくて、実際そうでした。 具体的に一例を挙げてみます。ある日、大学で一緒にやっていたキーボーディストの手書き譜面をチラッと覗き見したことがありました。それはもう一目見てたまげるくらい綺麗で正確な採譜でした。本人の演奏もまさにそんな感じで、それまで自分も採譜などには挑戦はしてはいたものの、なんとなくの雰囲気でやってたアライさんには衝撃的な譜面だったんですよね。今思えばあれが、やればあれくらいできるんだ、という明確なマイルストーンだったように思います。 アライさんはどちらもないですが、周りを見ているとヤマハ(ポピュラーコース)とかエレクトーンを習っていたフレンズはコードや理論なんかが包括的に扱える人が多い気がしますね。本人たちにそう言うとなぜか「とくにそこまでは習ってないけど」なんていうんですけどね。当たり前すぎて習ったことを忘れているのだと思います。それと、彼らも結局独自に興味を持って多くを独学しているのだと思います。 そんな感じで、結局身の回りで起きたことを大事にしていくのがいいのかなと思います。自分に関係ないパート譜を覗いてみたり、自分が例えばボーカリストであってもコードを読んでハーモニーを鳴らしてみたりというを、とにかくまめにやっていくといいでしょうね。自分で読んだ本、自分で鳴らしてみた和声、歌ってみたメロディしか身につかないところはあるので、その辺から取り組むといいんじゃないでしょうか!アライさんは長年、ハーモニーやら理論や記譜や読譜にかなりの劣等感がありましたが、なんとなくやってたらいつの間にかできるようになりました。休み休みでいつのまにか30年くらい経ちましたけどね。センスのあるフレンズが若いうちに集中して取り組めば5年や10年でなんとかなるんじゃないかなと思います。 あとは好きな本読むといいのだ。好きな本を。
スポンサーリンク
作(曲するア)ライさんさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク