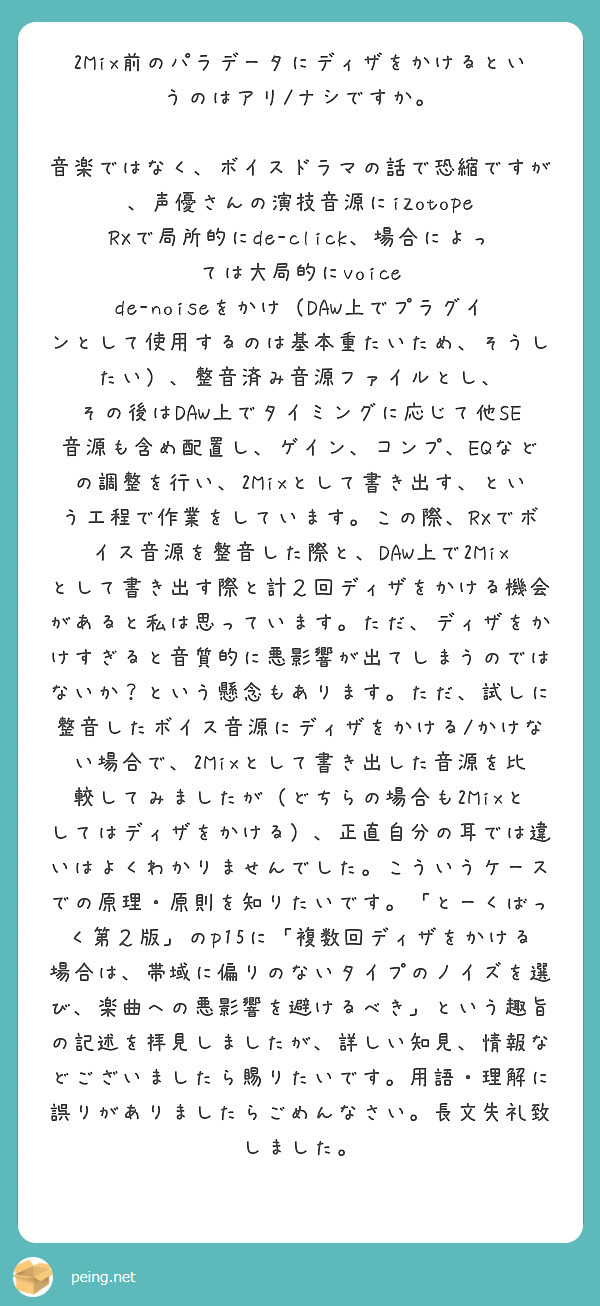拙著をご覧いただき、ありがとうございます。 質問者さんはすでにご存じかと思いますが、ここで念のためディザについておおまかにおさらします。 ■使用する目的 ビット深度を下げるときに、信号精度を維持します。 これは、単純なビットの切り捨て(Truncate)では生じる量子化誤差を軽減するために、意図的にノイズを加えることで実現します。 ■使用するべき場面 ビット深度を下げるときは、やらないよりはやった方が絶対マシです。 ただし信号がすでにクオンタイズされている場合は例外。 (クオンタイズの詳細については拙著をご覧ください) 上記原則に従った結果、ディザリングを複数回行うことになっても、それ自体は問題になりません。 逆にそうしないことにより量子化誤差が累積する方が、信号精度を維持する観点からはよろしくない、という見方もできるかと思います。 究極的には、信号がクオンタイズされているかどうかの管理がアタマの中でできていれば判断に迷う必要はありません。 ただし、そこまでこだわることに意義はあるか、また知覚可能な差が生じるのか…というとビミョーなところですよね。 ましてや質問者さんが実例として挙げられたように、長いコンテンツに対して局所的な処理を行う場合、クオンタイズされた箇所とされていない箇所が混在することもあり、どのように対処すべきかイチイチ考えるのも面倒です。 それよりは、たとえば「最終マスター以外は決して16bitで保存しない」といった、中間ファイルの品質管理の方がよほど影響がありますし、重要だと思います。 最後に「帯域に偏りのないディザノイズ」の件ですが、 お使いのRXの場合、Ditherモジュールの「Noise Shaping」がこれに関連します。 設定を変更すると、フラットなノイズ(None)から、高域にノイズを集中させたもの(Ultra)、またその中間のものを7段階ほどから選択できます。 モジュール内の簡易なスペクトラム表示からもわかるように、ここでは"None"が、偏りがなく、複数回重ねても同じ帯域にノイズが累積しないノイズということになります。
スポンサーリンク
David Shimamotoさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク