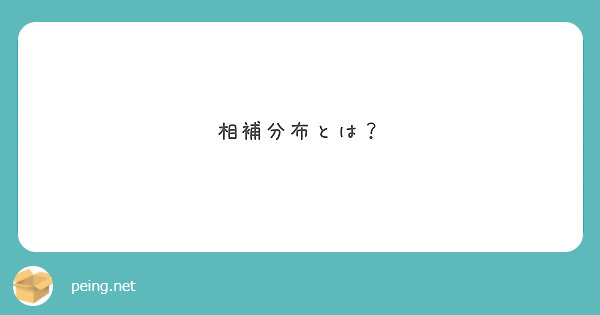相補分布というのは、一言で言えば、「ある言語のある音素の中の異音について、どういう時にどれが現れるのか決まっていること」を言います。 まず「音素」とは、ある言語において同じものと認識される音声学的な音を一つにまとめた抽象的な単位のことで、/ /で囲んで表記します。抽象的なので発音はできません。例として日本語の「ん」の音を挙げます。 「かんたん(簡単)」と発音してみましょう。この語には2回「ん」が登場しますが、それぞれ自分の口の中がどうなっているか観察してみてください。1つ目の「ん」では、舌先が上の歯茎についていて鼻から息を通して出す、音声学的には「有声歯茎鼻音」です。では、2つ目はどうでしょう?1つ目と違い、舌先は歯茎につかず、舌の後ろがのどちんこに触れて、その状態で鼻から息が通っています。これは音声学的には「有声口蓋垂鼻音」で、両者は音声学的には違う音です。ところが、これらは日本語の音韻においては同じ「ん」の音として認識されていますね。このように、「性質は違うけどある言語では同じ役割を果たしている音たち」をまとめたものをその言語の音素と言い、その中のそれぞれの音を異音と呼ぶわけです。 そしてさらに、どういう環境のときにどの異音が出現するか決まっているとき、相補分布をなしていると言い、この場合の異音は条件異音と呼ばれます。「かんたん」の例では、「ん」という音素が2拍目では有声歯茎鼻音という具体的な音となって、4拍目のは有声口蓋垂鼻音という音となって現れています。これは偶然ではなく、ここでは後ろに来る音の影響で必然的にそうなっています(逆行同化)。2拍目の「ん」は、直後に無声歯茎破裂音[t] が控えており、そのためこれと同じ調音点の鼻音である有声歯茎鼻音が出現しているわけです。 ちなみに日本語の「ん」には6種類の異音があって、直後に来る音によって綺麗に相補分布をなしています。
海斗さんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク