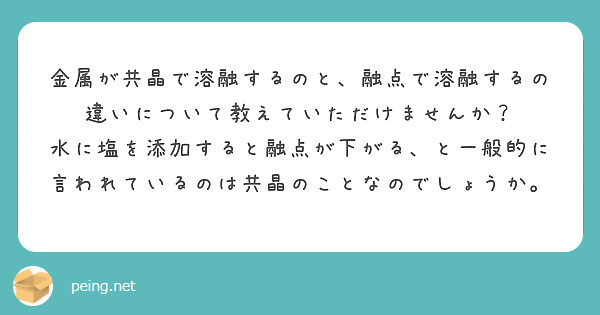10/27
二種類の金属(それぞれ金属A、金属Bとします)を考えます。純粋なAとBはそれぞれ特有の融点を持っていますので、低温から徐々に高温へ加熱していくと、それぞれの融点に達した時点で溶融します(水の場合は0℃ですね)。今度はこれらの金属を混ぜ合わせた合金を考えてみましょう。Aに対してBを少しずつ添加していくと、A-B合金の融点(正確に言うと完全に液体になる温度)はB濃度が高くなるほど低下していき(水に塩を添加したときと同じです)、純粋なAよりも低温で溶融するようになります。さらにB濃度を高めていくと、ある「特定の濃度」になったとき、融点は極小となって、それ以上Bを添加するとまた融点は上昇していきます。この極小の温度で合金が溶融する現象を共晶反応と呼んでいます。共晶反応が生じるような「特定の濃度」を持った合金を共晶合金といいます。逆に共晶合金を高温の液体状態から冷却していき凝固する際には、均一だった液体から二種類の結晶構造の異なる固体が晶出してきます。二種類の固体が共に晶出するので共晶と呼ぶのです。質問の答えになっているかわかりませんが、純金属と共晶合金の溶融挙動の最も大きな違いは、前者に比べて、後者は低温で溶融するということです。実用的には、材料をなるべく小さなエネルギーで溶かしたり固めたりしたいので、共晶合金は重宝されることになりますね。
スポンサーリンク
TSUCHIYAMA@Materialsさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
スポンサーリンク
過去に答えた質問
※利用規約、プライバシーポリシーに同意の上ご利用ください
スポンサーリンク