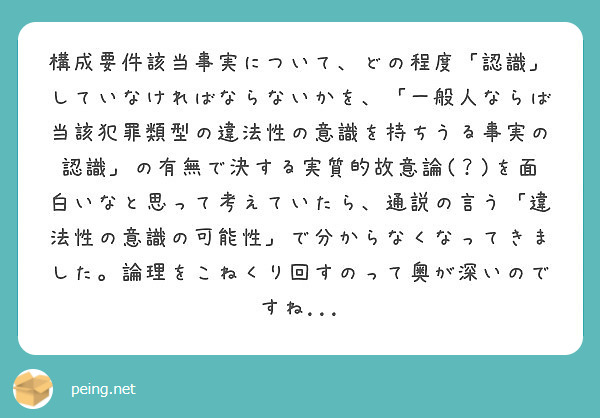7/27
事実の認識と,違法性の意識の問題を混同すると,そのような疑問が生じます。 ちなみに,38条1項がある以上,実質的故意論と言われる見解は解釈論として成立しがたく,学理では現在ほぼ駆逐されてしまったと理解されているようです。論者は,おそらくは訴訟における証明を考えておられるようなのですが,要件事実の問題と証明の問題とは切り分けて理解されなければなりません。 なお,学理は論理をこねくり回しているわけではなく,いかにして貫徹させるかに努力をしています。ただ,困ったことに,時々その論理を無視する人が出てくるので,学生の皆さんにも混乱を生じさせてしまうことになるのです。
スポンサーリンク
TSUJIMOTO, Norioさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
※利用規約、プライバシーポリシーに同意の上ご利用ください
スポンサーリンク