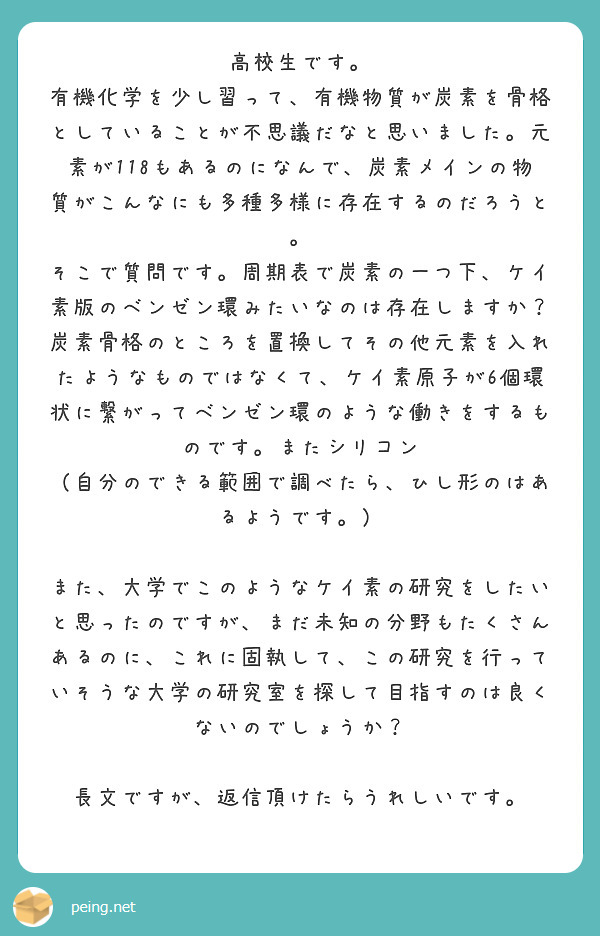「シラベンゼン」という物質ね。ベンゼンのCをSiに置き換えたものの総称で、置き換えるSiの数によってシラベンゼン、ジシラベンゼン、トリシラベンゼンと名前が変わっていきます。質問者さんの興味の的なのは、Cが6つともSiに置き換わったものなので、ヘキサシラベンゼン。科学の語彙で質問を書きなおすと、「ヘキサシラベンゼンは存在するか/合成済みか」ということになるね。どうかな、これで自分でももっと調べられるかな? で、ついでなのでヘキサシラベンゼンを調べてみましたところ、京都大学の時任宣博教授が2019年にヘキサシラベンゼンの合成研究計画についての報告書を出していました(とりあえずこれをググって見つけてみよう!日本語だから簡単に読めるし!練習練習!)。 ざっくり読む感じ、 ・ヘキサシラベンゼンの化学計算の報告はある ・まだ合成報告はない ・合成に使えそうな反応開発は成功した という感じですね。2019年から2年も経ってない段階でどこまで進んだのかは分かんないですけど、たぶんまだ合成できてなさそうです。未解決課題ですね、そそるぜこれは。 さて質問の後半ですが、高校生の段階で興味分野を定めて固執する必要は無いと思います。が、今回の場合は、とりあえず今の興味を大切にして京大を目指すという進路はアリだと思います。京大なら途中で興味が変わっても潰しが利きますし、あと教授が定年退職したり大学を変えたりしたときにも潰しが利きます。 興味を大切にしながら勉強を続けることと、ある分野に固執し続けることは、別のことです。私がオススメするのは、今自分が興味のある対象のより深い部分の興味を見つけ出すことです。例えば、あなたが興味のあるものは本当に「ケイ素」ですか?もしかしたら「既知の化合物を同族元素で入れ替える研究」なのかもしれないし、あるいは「化合物が安定に合成できるとはどういうことか」なのかもしれません。自分の興味が本当に深い部分でどこにあるのか、これは今後勉強していく中でもどんどん変わっていきます。そういう「あくまで自分の興味はこれで、これはこれで大切にしてるんだけど、もっと大きく見てみると真に重要なのってここだと思うんだよね」みたいな意識改革は、よく起きます。もしかしたら、炭素とケイ素について考えるためには酸素と硫黄の関係についてもっと調べないといけなくなるかもしれないですよね。そういうときに「いや、自分はケイ素なんだ!」と固執せずに「硫黄もやってみよう!」と言える柔軟性は(何歳になっても)大切だな~と感じます。 以上でーす。
スポンサーリンク
元素学たんさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク