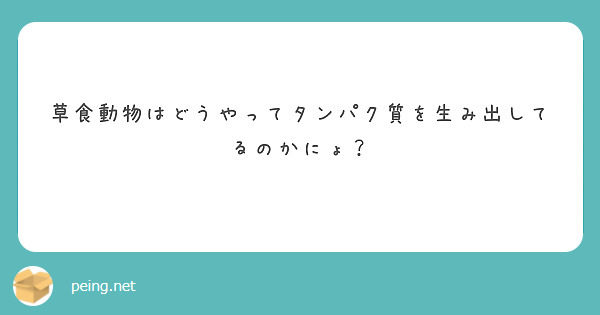草食動物は、セルロース(食物繊維)を分解できる微生物と栄養共生の関係をもっていて、菌体からタンパク質を得ているにょ。 なかでも馬はちょっと特殊なので、まず完全なる草食動物としての牛から解説を始めるにょ。 牛は4つの胃を持っていますが、まず第1胃は中性に近いpH値で、大量の微生物が生息しているにょ。ここで食べ物を発酵させ、第2胃で吸収しますが、まだ十分ではありませんにょ。 そこで行われるのが反芻で、いったん口まで吐き戻し、そこでふたたび咀嚼して飲み込むにょ。このとき、第1胃で仕事を終えた微生物の死骸も一緒に流れていき、第3胃で水分を吸収してから酸性の胃酸を分泌する第4胃でようやく消化され、腸に送られるにょ。そのときに菌体も一緒に吸収されるにょ。この菌体こそがタンパク質の源にょ。 このため、牛は自分ではほとんど何も消化しておらず、微生物の代謝産物と微生物の死骸を吸収しているだけにょ。つまり牛は摂取カロリーゼロでも生きていけるのですにょ。家畜としては理想的にょ。 ところが、草食動物としての牛の完成度に比べると、馬の草食生活はまだ無駄が多いにょ。 馬は胃袋が1つしかない代わりに巨大な結腸と盲腸を持っていて、ここに膨大な数の腸内細菌を共生させているにょ。盲腸だけでも1メートル、体積にして30リットルにもなりますにょ。 牛は「植物をまず共生細菌が利用し、次に細菌が生み出した栄養を牛が吸収」という方式でしたが、馬の場合は「まず馬が胃で消化吸収し、その残りを共生細菌が利用する」という方式にょ。 この順番が入れ替わっているために、馬は共生細菌の死骸をタンパク源として利用しにくいにょ。 そのため、馬は草を食べるだけではダメで、タンパク質を得るために穀物、芋類、豆類、アルファルファなどを食べる必要があり、これらを自分の消化酵素で消化する必要があるにょ。 馬が筋肉質に「見える」のは、筋肉の絶対量が多いからというよりも、体脂肪率が7–8%と低く、毛皮のテクスチャがなめらかで、筋肉の構造が立体的に見えやすいからにょ。 一般に、草しか食べない動物のほうが巨体にょ。それは、草の発酵と分解には長い時間がかかり、大量に体内に溜めておける消化管の容積が必要なためにょ。 ウサギも、馬と同じように栄養たっぷりの菌体成分を糞として捨ててしまっていますが、その糞を食べることで栄養を再吸収していますにょ。このおかげで、ウサギは草しか食べない動物としては異例の小さい体を保っていられるのですにょ。 コアラも巨大な盲腸でユーカリの葉を発酵させることで有毒成分を無毒化し、また糞食も行なっているにょ。しかし、ウサギのような高効率のエネルギー摂取はできておらず、1日のうち20時間は眠っているし、動作も緩慢にょ。 逆に瞬発力の必要な肉食動物は、PFP(pound for pound、体重あたりの戦闘力)が重要にょ。そして原則としてPFPは体格が小さいほうが有利になるにょ。 その理由は、体重は身長の3乗に比例して増えていくのに対し、筋力は筋断面積という半径の2乗に比例してしか増えないため、2乗3乗則により、サイズあたりのパワーは大きくなればなるほど落ち、のろまになっていくからでにょ。 実際、PFPで最強の生物といえばシャコやスズメバチなど、小型生物に多くなりますにょ。 陸上最大の肉食動物であるシベリアンタイガーは300kgですが、草食動物のゾウは7トンにもなるにょ。 肉食のホオジロザメは1トンですが、19トンにもなるジンベエザメはプランクトンしか食べませんにょ。 マッコウクジラは57トンで地球最大のキバを持つ動物ですが、それでも濾過摂食動物である200トンのシロナガスクジラにはかないませんにょ。 馬は、500kgというちょうどよいサイズで美しいプロポーションを保ち、優雅な走りをみせてくれるので、人間を惹きつけてやまないのでしょうねにょ。
スポンサーリンク
しあたんさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク