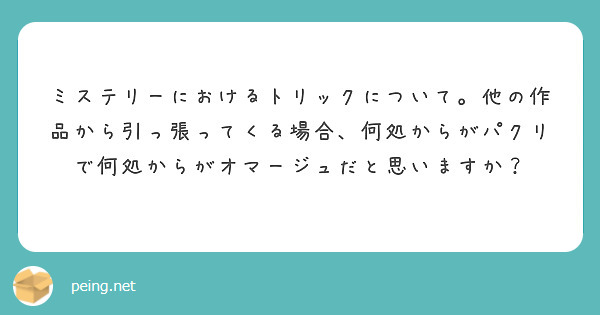これは難しい問題ですね。 一般的に、「元ネタを知られたくないのが“パクリ”」、「元ネタを知られても構わないのが“オマージュ”」、と区別されると言われていますが、こと、ミステリのトリックについてはもう、読者の捉え方に委ねる以外にないと思います。 いくら、作家が「オマージュだ」と言っても、読者が「いや、これはパクリでしかない」と感じてしまう可能性はありますし、逆に、作家は完全なパクリで、後ろめたい気持ちで作品を提出したとしても、「上手くアレンジしたオマージュだね」と解釈してくれる読者もいると思います。 ですので、私の個人的な考えを言わせていただければ、「オマージュだろうとも、他作品からトリックは持ってこないほうがよい」となります。 例えば、もし、誰もがそうだと分かるくらいに、過去作のトリックを上手くアレンジして、見事なオマージュに仕上げた作品を書けたとしましょう。ですが、「オマージュと分かるためには、元ネタを(読者に)分かってもらわなければならない」ということが前提にあるのであれば、当然、その元ネタであるトリックも読者に分かってもらう必要があるわけで、それはすなわち、「トリックの元ネタとなった作品のネタバレ」を同時に読者に食らわせることにもなってしまいます。これはあまりよろしくないのではないかな、と私は考えます。 ここに、他の分野(キャラデザインなど)とミステリのトリックとの「オマージュ」に対する決定的な違いがあります。 オリジナルのロボットをデザインするにあたり、「ガンダム」が大好きで、それをオマージュしたデザインを描くのであれば、「これは“ガンダム”のオマージュです」と、まず言い切る必要がありますし、それを言えないのであれば、そのデザインは“パクリ”の誹りを免れないかと思います。 同じことをミステリのトリックでやれる(言える)か? ということですね。 ただ、「意図しない偶然のトリックかぶり」は仕方ないです。殺人事件においては、「殺意の有無」が大きな争点となりますが、それと同じです。 余談になってしまいますが、じゃあ、「既存のトリックを知らなければ“パクリ”は起きようがないので、なるべく他の作家が書いたミステリを読まないほうがいいのか?」と思ってもしまいますが、そこがミステリ書きのジレンマで、個人的な考えですが、「ミステリを上手く書く能力は、ミステリの読書量に比例する」と私は感じています(一部の天才を除き)。 「読めば読むほど強くなる」しかし、「読めば読むほど“トリック”を知ることになって、“偶発的なトリックかぶり”が起きにくくなる」というわけです。 というわけで、質問の答えとしては、「“パクリ”か“オマージュ”か、それを決めるのは作家の良心次第」で、さらには、「読者の捉え方によって、“パクリ”にも“オマージュ”にもなる」という、身も蓋もない回答になってしまいます。 長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
庵字さんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク