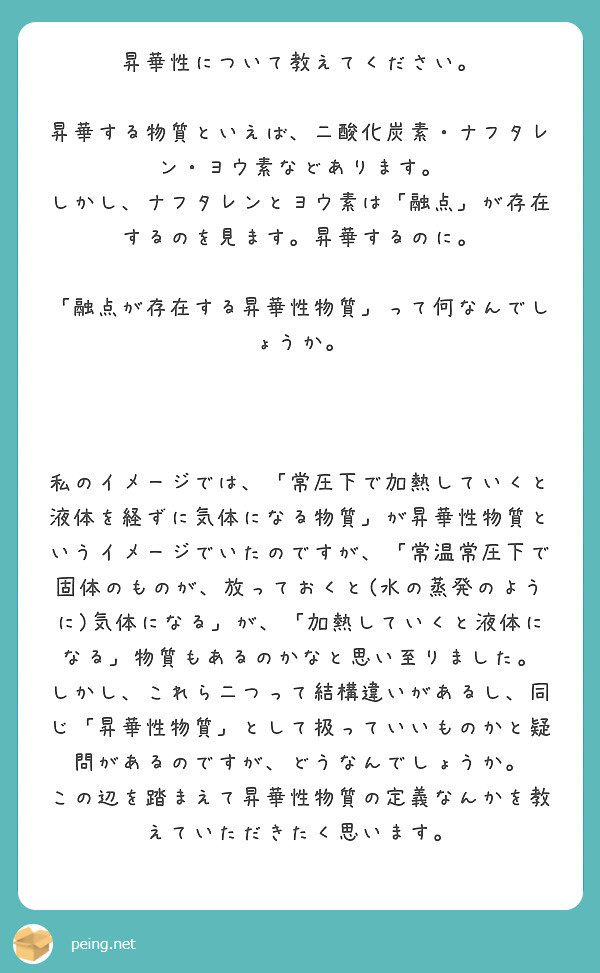なるほど、分かりやすい質問で助かります。 結論から述べると、質問者さんの推察の通り、昇華性には二種類あります。ひとつは「状態図において1atmのとき液相が現れないので昇華する」ものと、「状態図において1atmのとき液相が現れるのだが、固体の蒸気圧がかなり大きいため昇華する」ものです。挙げられている例でいうと、CO2は前者、I2やナフタレンは後者です。例として、CO2とI2の状態図へのリンクを掲載しておきます[1,2]。 「原理の異なる現象を一緒くたの名前で呼んでもよいのか」という質問者さんの疑問はもっともだと思います。一応なぜそうなっちゃってるかを考えてみると、昇華という言葉は単に「液体を経由せずに固体が気体になる」という見たままの現象に与えられたものであるからでしょう。日本語としての化学用語「昇華」の初出は1833年で[3]、これは物理化学が成熟する19世紀末~20世紀初頭よりもかなり前なので、この時代には相転移のことはほとんど分かっていなかったはずです。なので、状態図上で液相がないタイプの昇華と、液相はあるが蒸気圧がめっちゃ高いだけの昇華を、峻別することは困難だったでしょう。この言葉遣いを(少なくとも高校化学では)現代まで引っ張ってしまっているので、こういうバグが発生しています。気持ち悪いかもしれませんが、バグがあることを理解していれば多少耐えられるでしょう。 というわけで、昇華の話でした~。 [1] CO2の状態図 https://info.ouj.ac.jp/~hamada/TextLib/rm/chap6/Text/Cr990603.html [2]I2の状態図 https://www.researchgate.net/figure/Phase-diagram-of-iodine-retrieved-from-http-chemwikiucdavisedu-Textbook_fig1_312596421 [3]函館工業高等専門学校紀要(第 51 号) https://www.jstage.jst.go.jp/article/hakodatekosen/51/0/51_1/_pdf
スポンサーリンク
元素学たんさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク