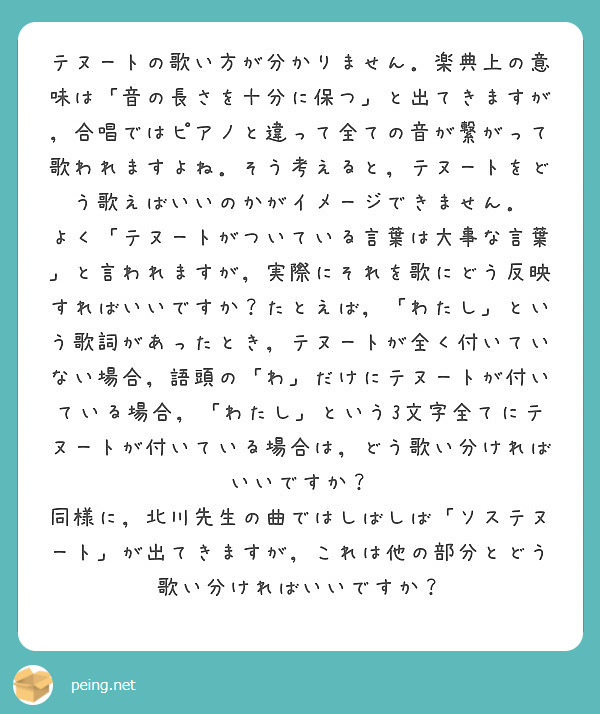テヌートに限らないのですが、アーティキュレーション記号の元の意味に囚われすぎると、演奏がチープになってしまうことが多いです。 例えば、スタッカートがついてるから「短く切って」演奏することは間違いではないのですが、その場面の表現に即した短さというものがあるので、どの程度短くするとか、本当に全て同じ短さになるのかとか、そういうことの検証は必要です。 テヌートの「音の長さを十分に保つ」という意味は、実はとても抽象的な表現です。なので、先述したスタッカートのように「その場面に即した(適した)表現」というものを考える必要があります。「作曲家が何を意図してテヌートを付けたか」を考えるとも言えるでしょうか。 例に挙げられたことでいうと、「わたし」の「わ」にだけテヌートがある場合は、語頭の「Wa」に何らかの工夫を施してほしいという作曲者のメッセージが想像できます。「わたし」全てにテヌートがあるのであれば、「Wa-ta-shi」という言葉全体に工夫がほしいということですね。 「どう歌い分ければいいか」という問いに対しては、「正解は無い」という元も子もない回答しかできません。書いてあることをどう捉えるかは十人十色ですし、場面に応じて同じ言葉でも違う表現になることがあるからです。 ですが、考え方としては「テヌートが付いている音符をどうにかする」ということに加えて、「何も付いていない音符と比較してどうするか」という観点も加えてみてください。 つまり、アーティキュレーション記号が付く音符に「盛る」だけではなく「浮き彫りにする」ために周りの音符に「引き算」を施すということも、時には考えていただきたいのです。 (ちょっとわかりにくいですかね…。私のレッスンや講習会だとこの話をさせていただくことが多いので、どこか直接聞いていただける機会があると良いのですが…。) sostenutoについては、場面によりけりではありますが、meno mossoと似た意味で使っていることがあります。短い時間だけテンポを落としてほしい時に使っていることが多いはずです。sostenutoの後にa tempoがあったら、そう捉えていただいて結構です。
スポンサーリンク
Noboru KITAGAWAさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク