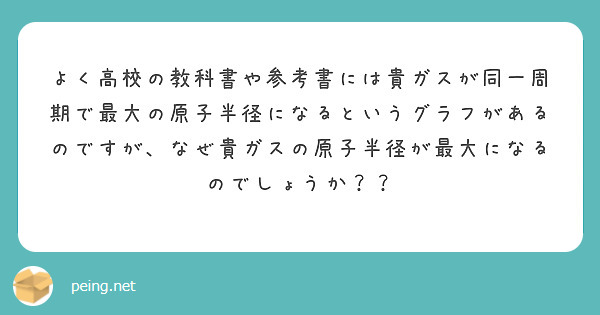この質問を見たとき、最初何を言ってるのか分からなかったのですが、どうも化学教育上マジで良くないことが起きているらしいことが分かったのでコメントします。 まず最初に言っておきたいのは、「同一周期内で貴ガスの原子半径が最大になる」ようなことは事実としてありません。つまり、その教科書だか参考書だかのグラフは、間違えています。実際は、原子半径は(正確には共有結合半径は)同一周期では周期表の右に行くほど小さくなる、逆に言えば1族のアルカリ金属の原子半径が同一周期内では最も大きくなります。 ではどういう間違いを犯しているかというと、「共有結合半径」と「ファンデルワールス半径」という測定対象の全く異なる半径を一緒くたに扱うというミスを犯しています。 あまりピンと来ないかもしれませんが、「原子の半径を測定する」というのは口で言うほど簡単ではありません。化学では原子を「粒子」などとさもビー玉のようなイメージで呼ぶことがありますが、実際はビー玉のようなしっかりした球体ではなく「モヤモヤした雲みたいな何か」って感じで、どっからどこまでが半径か極めてわかりにくい状態になっています(原子のまわりの電子が雲っぽい感じになっており「電子雲」と呼ばれます)。そのうえ雲っぽいのですから、その原子がおかれた環境(ほかの原子と共有結合してる最中なのか、真空にぽつんとひとりでいるのか、結晶中に閉じ込められているのか、などなど)によって形状も変化します。ここで研究者はややこしい問題を抱えます。「我々はどの状況にある原子のどこの長さをもって「原子の半径」と呼べばよいのか?」この答えは必ずしも一つには定まりません。何を「原子の半径」とするのが直感に沿うのか、あるいは便利なのか、研究者によってまちまちだからです。しかしいろいろ考えてるうちにおのずと「ここの長さを半径って考えたら多くの場面で便利では?」という有力な定説が絞られてきます。 その有力な定説のひとつが「共有結合半径」で、また別のひとつが「ファンデルワールス半径」です。この二つの半径の違いを一言で表すなら、共有結合半径は「共有結合したことで二つの球が互いに食い込んでいるような状態での球と球の中心間の距離」をもとに、ファンデルワールス半径は「二つの球がちょうど一点で接している状態での球と球の中心間の距離」をもとに算出しています(この二つの違いは図示されれば一撃で理解できるのでどこかで図を見てください)。 さて、ちょっと考えてみてください、このようにして定義された共有結合半径とファンデルワールス半径、単純に比較できると思いますか?どう考えても互いに食い込んでいる分だけ共有結合半径のほうが小さい値になると思いませんか?当然そうなります。ある原子において、「共有結合半径」と「ファンデルワールス半径」の二種類の半径が測定できますが、この二つの大小関係は 共有結合半径<ファンデルワールス半径 となります。 貴ガスの話に戻ります。「同一周期では貴ガスが最も原子半径が大きい」という主張は上記の過ちを犯しています。貴ガス以外の元素では共有結合半径の値を採用しつつ、貴ガスではファンデルワールス半径の値を採用しているのです。そりゃあ貴ガスのほうが大きい値になるに決まってんでしょ!馬鹿じゃないの!?っていうかそんなことやっていいなら酸素の共有結合半径(約74 pm)とフッ素のファンデルワールス半径(約150 pm)を比較したらフッ素のほうが半径大きくなるっつーの!はい周期表の傾向崩れた~周期表おわり~ってなるわけないだろボケ!!!同じ尺度同士を比較するから意味あんだよ!!!科学する気あんのか!!!!!帰って寝ろ!!!!!!!!!! ということなので、どうか間違えないようにね♪ 追伸1:それでは、共有結合半径とファンデルワールス半径、片方の測り方で統一した表を作ることはできないのでしょうか?また作れたとして、そこではやはり「周期表で右にいくにつれ原子半径は小さくなる」が言えるのでしょうか? まず共有結合半径についてですが、貴ガス元素の共有結合半径を実測するのは困難であると思われます。貴ガスは共有結合を起こしにくいためです。ただし全く起こさないというわけでもなく、近年は貴ガス化合物の合成報告がぽつぽつ挙がるので、そのうち実測されてすべての原子半径を共有結合半径で書ける日が来るかもしれません。ただし、今はまだ無理といってよいと思います。 次にファンデルワールス半径ですが、こちらは可能性があるのかなと個人的には思っています。何より化合しにくい貴ガスにおいて実測データが得られる尺度というのは魅力的です。ただしいくつか教科書を見ている限り、どうも表の埋まりは良くないような気がします。測定が難しいのでしょうか。あるいは別のアプローチとして、量子化学計算といった方法で半径を計算して求めることが最近では試みられているらしく、それが良いデータとなるかもしれません(まあただ、最終的には計算精度を実測でチェックすることになるような気がするので、どれぐらい上手くいくのかは分かんないです)。 そういうわけで、私の今のところの結論としては「貴ガスを空欄にして共有結合半径の一覧を示すのが最も誠意的」です。 追伸2:高校化学の授業でこの話題がどこまで繊細に扱われているかは分かりませんが(先生によると思う)、受験で原子半径の話題が出た際は貴ガスを除いて考えるように指示があるとのことです(現役の高校化学教師から教えていただきました)。なので試験の点数に影響するような事故は起きていないものと思います。安心してください。
スポンサーリンク
元素学たんさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク