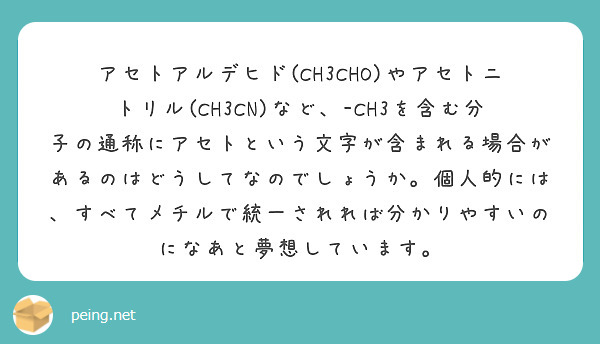これ分かりにくいよね。「アセト」という接頭語は、実は-CH3を示しているんじゃないんです。 CH3CO-、つまりメチル基とカルボニル基が結合した一連を「アセチル基」と呼びます。Acと略すことが多く(これ知らないと有機化合物に急にアクチニウムが出てきたように見えて焦る。化学初学者あるある)、例えば酢酸はAcOH、酢酸アンモニウムはAcONH4などと略記出来ます。「メチル基とカルボニル基は単独で名前があるんだから別の名前で呼ばなくてもいいじゃん!」ということは私も最初思いましたが、この一連のパーツを化合物に付けたり外したりすることが頻繁にあるのでまとめて呼ぶ語彙があった方が便利なんですね。 アセチル基を持つ物質の名前に「アセト」がつくことがあります。たとえばアセト酢酸という物質はAc-CH2COOHという構造です。これって要するに酢酸のメチル基のHひとつがアセチル基に置き換わったもので、なのでアセト酢酸という名前です。ほかの例としては、たとえばアセトアミノフェンなど、たくさんあります。調べて構造を確認してみてください。 「アセト」が構造を表す場合、指し示しているのはCH3CO-です。しかしこれでは少なくともアセトニトリルの「アセト」の説明にはなっていません。 「アセト」にはもうひとつ、「酢酸(acetic acid)を起点にして合成された物質」という意味があります。これは歴史的な語彙で、そもそも官能基というものの存在がよく分かっていなかった時代に化合物をどうやって名付けるかという話になります。acetic acid から作られたのでacetaldehyde(アセトアルデヒド)だしacetonitrile(アセトニトリル)なわけです。 ところで、酢酸にはアセチル基があるので、酢酸から作られる物質はアセチル基を持っていることが多くあります。というかそもそもアセチル基 acetyl group という名前がacetic acidが持つ官能基というところから来ているわけです。しかしacetic acid由来の物質がすべてCH3CO-構造を維持しているとは限らないわけです。なのでアセトニトリルのようなアセチル基を持たない「アセト」が現れてしまったわけです。これは現代を生きる私たちにはややこしい話ですが、当時の化学者はそもそも原子や分子の存在にすら確信がなかったので、歴史的に仕方のないことですね。 まとめると、こんな感じです。 ・まず酢酸 acetic acid があった。 ・酢酸から導かれる物質を原料名を使って「アセト~」と名付けた。(歴史的な「アセト」の用法) ・次第に化学構造という概念が発達しアセチル基が発見された。 ・アセチル基を持つ化合物を「アセト~」と名付けることにした。(構造由来の「アセト」の用法) 以上でーす。
スポンサーリンク
元素学たんさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク