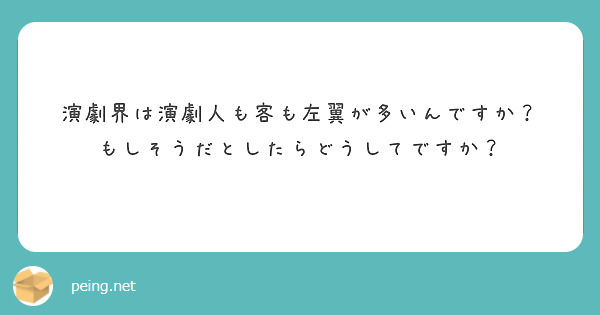まず、演劇界にはいわゆる「政治的な人間」が多いように私は思います。「政治的な人間」とは、「一人一人の言動が社会を変える力を持っている」と信じている人のことです。 また一般論として演劇のテーマはリベラルと親和性が高く、ギリシャ悲劇の時代から戦争に巻き込まれたり、権力者の弾圧に抵抗したり、家父長制に抗う人の葛藤が描かれ易いです。勝ち馬に乗ってるだけではドラマは生まれませんから。 つまり、もともと作り手も観客も左翼的な内容の演劇に触れる機会が多いです。 では、実社会の政治的立場はどうかと言われれば、たしかに演劇界には伝統的に左派の人は多いです。 第一次大戦後にプロレタリア運動に合わせて世界規模で左翼演劇が流行りました。日本でも築地小劇場が出来た時は芸術至上主義を標榜していたんですが、若い人たちを中心に左翼思想がどんどん入り込んできて、ついには思想の衝突が原因で分裂し、以降、日本の近代演劇は社会主義の実現を目指す左翼演劇と、政治的なイデオロギーは排してあくまで芸術至上主義を標榜する二派に分かれて発展することになりました。 左翼演劇の方は、芝居の稽古そっちのけでマルクスの勉強ばっかりしてましたし、演技方法も「全ての演技は社会主義を実現させるためのセリフと動きでなければいけない」という荒唐無稽なものになりました。 やがて戦火が激しくなるとになると、当局による思想弾圧で、左翼演劇の人たちは逮捕されたり、転向させられたりしました。 ほとんどの劇団が解散させられましたが、僅かな例外として、芸術至上主義を標榜していた文学座や、戦意高揚の演劇を作らされていた宝塚歌劇団や、忠臣蔵など歌舞伎の演目が当局に喜ばれた前進座などが戦時下を生き延びました。 ドイツは降伏した後、国が分割されて社会主義の国と、資本主義の国に分かれましたが、日本の場合はGHQの政策で国体が保持されたので、一国の中に、二つの対極したイデオロギーが共存したまま戦後が始まりました。そして「反戦」がとても大きなテーマになりました。 そして、戦前に思想犯として捕まっていた左翼演劇人たちが釈放されて再び結集すると、弾圧の反動もあって左翼的なイデオロギーを持つ演劇グループがとても強大になりました。代々木系(日本共産党)との結びつきも強くなり、前進座などは劇団員全員が一斉に日本共産党に入党したほどです。 1960年代には、政治的なイデオロギーを排していたはずの文学座の中にも共産主義傾倒者がかなり増えていて、三島由紀夫が踏み絵の如く反共的な芝居を書き、脱退する事件なども起こっています。 結局、この時文学座が拒否した三島作品を上演した劇団四季のように、左翼に与しないという確固たるポリシーを掲げる劇団もありましたが、この頃には「新劇と言えば左翼」くらいの影響を持ちました。 そして観客に関しても、全国の労働組合などが後援になりましたので、当然作品も左翼色が強いものが増えます。つまりこの時期は、やってる人もそれを支える観客も結構ガチな左翼の人が多かったことがわかります。 意外ですが、この風向きを変えたのはアングラ演劇(小劇場第一世代)でした。 寺山修司は60年安保に対する幻滅からイデオロギーからの乳離れをして「書を捨てよ町に出よう」を書いたと言っています。 蜷川幸雄は元々割と熱心にデモとか行ってたんですが、現代人劇場で新左翼と足並みを揃えた芝居をやっている中で「お客さんとのズレ」が拭えなくなって、解散します。ちょうど連合赤軍事件が起こった時で、多くの一般客は新左翼に対して嫌悪感を抱くようになっていたのです。 清水邦夫は、新左翼の思想には共感しつつも、自分自身は直接的な政治活動はせずに芝居の中だけでやろうとしました。でも結果として、若者たちを新左翼思想にアジテートしてしまったと、後悔を口にしています。 鈴木忠志は、かつて自分の芝居を観に来た文化人に「お前スポイルされるぞ」と言われたのに対して「左翼は政治的な情勢を信じすぎる。人間はそんなふうに動いてない」とはっきり言い、またそういう次元からは足を洗って左翼的な演劇界とは付き合いたくないと言っていました(その後実行に移しました)。 唐十郎は、先輩にオルグされて仕方なくデモに参加したけど、劇団の旗を持って、変わった装束を着て参加してたら「ふざけるな。政治はシリアスなものだな」と怒られて、それ以来、政治が嫌になったと言っています。 てな具合に、かつての新劇人たちが演劇を通じて「実際に」共産主義革命を目指していたのに対して、小劇場第一世代であるアングラ世代は実社会における政治闘争をかいくぐっている割には、現実の政治からは一歩身を引いた演劇人が多かったのです。もちろん実際に政治運動をしていた演劇人も中にはいますが、多くの人はかわりに演劇に革命を起こしました。少なくともそれまで日本の演劇界とズブズブの関係だった代々木系(日本共産党)イデオロギーとは絶縁しました。 にもかかわらず、時代の空気もあってか、みんなやっぱり闘争とかそういうのは好きなんですよね。パルコ劇場に対してストライキやるぞと言ったり。それを野田秀樹が「まあまあ」と言ってなだめたりしてるんですが、新左翼の敗北から、世の中が政治的に冷めてきて「一人が声を上げたからって世の中変わりゃしないよ。そんな熱くなってどうすんの」という白けた空気になってきました。そんな時代の空気を敏感に感じ取った若い人たちが中心となって小劇場ブームが起こりました。でも長くは続きません。演劇は客商売なので「お客さんとのズレ」を感じとらずにいると当然客足は遠のいていきます。 最近の話で言うと、3.11以降ずっとズレ続けてたんですが、そのズレが決定的に露呈したのがコロナ禍の演劇バッシングだったと思います。 若い人には、昔の夢を諦めきれないシルバー左翼演劇人に取り込まれないように気をつけて、時代の空気に対して敏感であってほしいと思います。
スポンサーリンク
王様はロバさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク