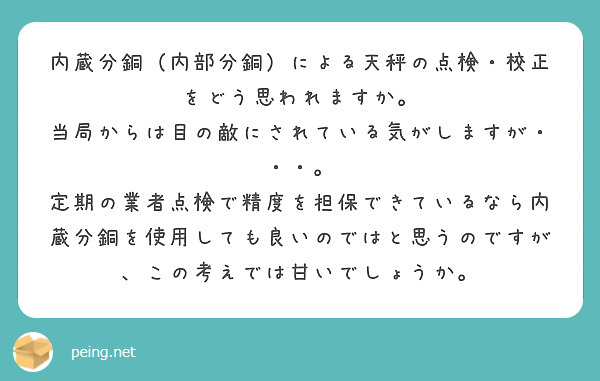電磁式天秤の内蔵分銅(内部分銅)については、色々議論されていますが、内部分銅での点検校正の仕組みと、できることの限界を知る必要があります。 島津製作所のサイトに内部分銅について書かれているところがありましたので、抜粋します。 https://www.an.shimadzu.co.jp/service-support/technical-support/analysis-basics/balance/hiroba/qa/03/index.html#qa01 Q. 校正分銅内蔵形の天びんはどのようなメカニズムで校正を行なう仕組みになっていますか。また、校正分銅内蔵形の天びんを使用すると、ISO9000やGLP、GMPなどの点検に際して、外部分銅は必要ないですか。 A. 校正分銅内蔵形の天びんはその内部に校正用の分銅(計量法上は「おもり」)をもっており、それをモーター駆動機構などにより内部で載せ降ろしができるしくみになっています。元々はこの「おもり」そのものには質量の値付けがされているわけではなく、この「おもり」を載せたときの荷重値を、標準となる外部分銅を載せたときの荷重値と比較し、外部分銅の質量のどれだけに相当するかという値を記憶させています。こうすることにより、天びん内部の「おもり」に、標準となる外部分銅の代わりをさせることができ、天びんの感度校正が行える仕組みです。 標準となる外部分銅で校正した値と、内蔵分銅による校正値が同じであることが一度確認できれば、通常使用する上でズレが生じてくることは少なく便利ですが、長期間使用する間には様々な要因によるズレが発生するリスクがあります。外部分銅を用いて内蔵分銅(おもり)による校正が正しく行なわれているかの確認や、定期的に標準となる外部分銅を用いた点検が必要です。 こちらは、新光電子のサイトにあった記載です。https://information.vibra.co.jp/faq Q:校正分銅内蔵タイプのはかりを購入すれば、分銅は必要ありませんか? A:新光電子では、分銅内蔵タイプの製品シリーズもご用意しております。分銅を用いず、ワンタッチで調整が行えるため非常に便利な機能です。 半面、内蔵分銅は正確には分銅ではなくトレーサビリティのない「調整用おもり」ですので、調整を行っても「校正(=重量チェック)」をしたとはみなされません。 また内蔵分銅は経時変化もいたしますので、最終的には外部分銅による重量チェックを行うことをおすすめいたします。 この記載によると、内部分銅は、1点での管理で、センサー部分以降の確認になるということです。秤量皿からセンサー部分までは、確認できないということになります。また、内部分銅自体は校正や値付けがされているわけでもなく、おもりという位置づけになります。 内部分銅による点検校正でできることは、今、GMPで要求されていることの一部のみになります。 島津製作所のサイトに、日常点検と定期点検の例があります。 ・日常点検の項目例 (1) 天びんの皿や周囲が汚れていないか (2) 水平がでているか (3) 表示がばらついているなど異常はないか (4) ひょう量は合っているか ひょう量の点検は質量の分っている分銅を皿に載せその表示値との差が基準値(使用者が品質要求に対して定めた数値)以内にあることを確認します。基準値を越えた場合の処置も手順書で決めておく必要があり、再調整を行って基準値内になったことを確認するか修理に出すなどの手順を決めておきます。 ・定期点検の項目例 (5) 繰り返し性 (6) 偏置誤差 (7) 器差或いは直線性の点検を加えます 上記の日常点検にもあるように、「(4) ひょう量は合っているか」では、「質量の分っている分銅を皿に載せその表示値との差が基準値以内にあることを確認する」 となっており、内聞分銅の点検・校正だけではなく、実際の分銅を載せての確認を求めています。 また、私の知っている範囲でいいますと、 日常点検において、定期点検での「(5) 繰り返し性」、「(7) 直線性の点検」も行っている場合を多く見かけました。 使用する分銅は、よく使用する値や、使用する可能性が高い範囲(3点くらい)を見ています。 内部分銅での点検校正は、日常点検の一項目に過ぎない扱いです。 使用されている天秤がわかりませんので、何ともいえないのですが、 GMP・GLPなどの対応に強い、天秤メーカーに確認・相談されるのがよいかと思います。 (島津、ザルトリウス、メトラーなど) 特に、メトラー、ザルトリウスは、グローバルですので、昨今天秤への要求を強めているUSPをはじめとする情報も、サイトに掲載されていたり、提供いただけたりすると思います。 メトラー:https://www.mt.com/jp/ja/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Service/compliance/weighing-quality-assurance-plan-for-balances-and-scales.html いずれにしても、自分たちが、自信をもって説明でき、示すことができるデータであり、点検をはじめとする方法であるように努めることが大切だと思います。
スポンサーリンク
Y_G_M_Pさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク