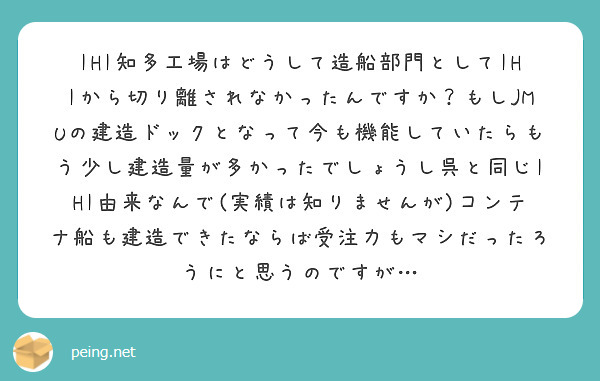ご質問ありがとうございます! IHI知多工場がなぜJMUの設備にならず破棄されたのかということですが、これは①IHIの成り立ちと、②造船不況時に国策として行われた設備処理が関係しております。 ①IHIの成り立ちについてですが、IHIは1960年に石川島重工と播磨造船の2社が合併して誕生した企業です。 この合併の目的は、播磨造船にとっては「自社の売り上げの9割を造船に依存している現状の改善」の為であり、石川島にとっては「陸上部門の比重が高く経営は安定しているが、大型船台が無くタンカー大型化についていけない」という両社の問題を解消するためのものでした。 両社の設備は、石川島側は東京、播磨川は相生と呉でした。 横浜は1964年、知多は1973年に稼働を始めたもので、合併後に計画建設された設備です。 ②改めて設備処理を説明すると、1973年のオイルショックに伴う造船不況で、日本政府は過剰設備の処理(閉鎖や譲渡、造船以外への転換など)を各造船企業に求めました。1980年の事です。 詳しくはブログ内の造船研究をご覧ください。 当時、IHI(石川島播磨重工業)には自社設備の約40%の処理が求められ、知多工場はその際に処理(造船建造からの転換)されることとなりました。 そして、設備処理は人員の配置転換や削減が必要不可欠であるといえます。 その際にどの設備を処理するか。 経営陣の判断としては、古くからある造船所を守ると言う決断だったと伺えます。 ※当時のIHIには東京、横浜、愛知(知多)、相生、呉と子会社(IHI造船化工機)があり、この内東京の船台1基、横浜と愛知のドックを処理した。 その後、1990年台には規制も自然消滅していき、知多でも建造が再開されるものの結局96年頃に再度停止し、2008年頃に再び再開されるものの2012年頃には再度停止しました。 IHIの他の造船所はこのような運用はされていないことから、あくまでも好況期のみ船舶建造を行う設備として認識していたといえます。LNG船用のタンクや海洋構造物などの製造拠点になっていたことから、主として船舶建造を行うという運用方法は無かったのでしょう。 言い換えると、タンクや海洋構造物関係の事業を中止すると、工場は不要になるとも捉えられます。 ご質問の回答としては、結局のところ、「設備処理で知多は造船事業部から事実上捨てられていた」ことが大きく影響していると考えられます。 ※ちなみに処理された横浜は現在JMUの横浜事業所として艦艇建造を行ってます。商船ではなく艦艇の建造として生き残ったと言えますね。 もしもIHIマリンユナイテッドの設備として運用され、JMUに統合されていたら面白い展開があったのかもしれません。 津と知多は伊勢湾を挟んで対岸にあり、約1時間もあれば車で到着できます。 津は2万TEUサイズの建造も数値上は可能な広さを持ってますし、LNG船の建造ならIHI独自のタンク技術を使い、有明で原油タンカー、呉でコンテナ、津と知多でLNGタンカーなどもあったかもしれませんね。
スポンサーリンク
ことへいのお部屋さんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク