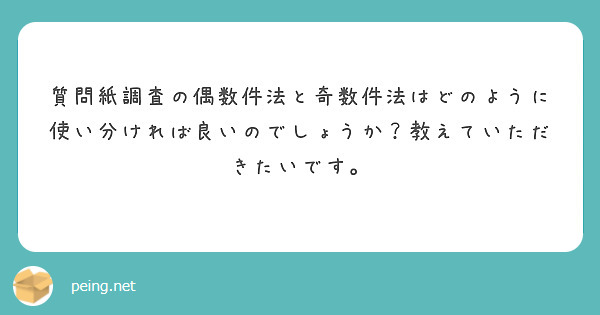奇数件法と偶数件法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。 奇数件法とは、「とてもそう思う」「そう思う」「どちらでもない」「あまりそう思わない」「全くそう思わない」という5件法のように、選択肢の数が奇数で、中央に中立的な選択肢を設ける形式です。 この形式のメリットとしては、 調査テーマについて意見が定まっていなかったり、本当に中立的な立場だったりする回答者は、「どちらでもない」を選ぶことで、無理に意見を表明する必要がなくなるため、回答者の心理的負担が軽減します。また、無理に肯定・否定のどちらかを選ばせることによって生じる測定誤差(回答者が本心とは違う選択をするリスク)を減らし、より正直な回答を引き出せる可能性があります。 一方で、回答が中央の選択肢に集中しやすくなる中心化傾向 (Central Tendency Bias)が発生する可能性があります。これにより、データ全体の分散が小さくなり、グループ間の差や意見の分布が見えにくくなることがあります。特に、断定的な表現を避ける傾向のある日本では、この傾向が顕著に見られることが報告されています。また、「どちらでもない」という選択肢は、(a)本当に中立な意見、(b)質問の意味がわからない、(c)関心がない、(d)答えたくない、といった多様な意味で解釈されうるため、分析の際に注意が必要です。 他方で、偶数件法とは、「とてもそう思う」「そう思う」「あまりそう思わない」「全くそう思わない」という4件法のように、中立的な選択肢を設けず、肯定的か否定的かいずれかの立場を選択させる形式です。強制選択法 (Forced Choice Method) とも呼ばれます。 この形式のメリットとしては、 中立の選択肢がないため、回答が中央に集まる中心化傾向を防げます。また、回答者に意識的な判断を促し、潜在的な態度をより明確に引き出す効果が期待できます。肯定派と否定派の比率などをクリアに把握したい場合に有効です。 一方で、本当に中立な意見を持つ回答者は、自分の意見に合致する選択肢がないことに困惑する可能性があります。これは、無回答やいい加減な回答(ランダムレスポンス)につながり得ます。また、回答者を無理やりどちらかの立場に追いやることで、かえって実態とは異なるデータ分布が生まれる可能性があります。 使い分けを大まかに整理するならば、回答のしやすさと自然な意見分布を優先するなら奇数件法、意見の明確化と態度の顕在化を優先するなら偶数件法といったところでしょうか。 詳細は以下の論文などもご覧ください。 Chyung, S. Y., Roberts, K., Swanson, I., & Hankinson, A. (2017). Evidence‐based survey design: The use of a midpoint on the Likert scale. Performance improvement, 56(10), 15-23. https://doi.org/10.1002/pfi.2172
Daiki Nakamuraさんになんでも質問しよう!
質問
スタンプ
利用できるスタンプはありません。
スポンサーリンク
過去に答えた質問
スポンサーリンク